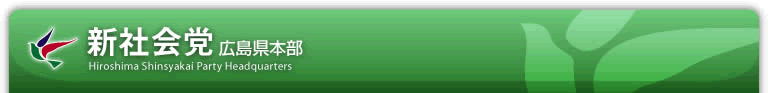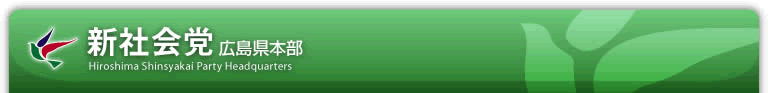|
|
|
【10月号】文楽」あれこれ 3 則藤 了
|
|
2012/12/16
|
少し時を遡るが、竹本義太夫の高弟、美声の竹本采女は、自分の弟子たちを連れて新たに豊竹(若太夫)座を起こした。一方義太夫は小音悪声だが人物を深く掘り下げる若手の政太夫を後継者に指名し、以降地味な語り口の竹本座と、派手で艶っぽい語り口の豊竹座は、道頓堀の西と東にあって、それぞれ西風、東風と呼ばれて競い合い、ともに発展していくが、やがて歌舞伎の人気に圧されて、1770年代になると、共に閉座のやむなきに至る。
これから人形の衰退期を迎え、道頓堀の盛り場から姿を消した人形芝居は、宮地芝居と呼ばれる、神社の境内に小屋掛けした半公認の芝居となっていくとともに、次第に新作が減って人気のあった旧作の繰り返し上演が多くなり、所謂古典化への道を辿っていく。
1770年代、最後の灯火のように活躍した近松半二、菅専助を最後に、本格的な作者はいなくなり、旧作の繰り返し上演が多くなるが、一方、そのことにより、旧作を繰り返し語る太夫や三味線弾きは、自分の芸に工夫を凝らし、それぞれの芸風というものを確立してゆく。この時期を一般に衰退期と呼ぶが、道頓堀の繁華街からは姿を消したものの、あちこちに小さな小屋が乱立し、多くの名人が出て、むしろこの時期にこそ、義太夫節が芸としての充実期を迎えたとも言え、この時期に語った名人の語り口は何々太夫風として、後世まで尊重される。人形浄瑠璃は古典化することにより、芸としての爛熟期を迎えたのである。
こうした爛熟期に、文学的に優れた近松の作品が再演されなかったのは、近松没後百年近くもたっており、義太夫節の語り口も人形の大きさ、構造も大幅に変化しており、とてもそのままの文章では舞台に掛けられなかったからである。ここに今日まで残る近松作品が改悪と言われながら後代の改作物ばかりである理由がある。
この頃(18世紀末)、淡路から大阪へ出て来た興行師の植村文楽軒は、高津の地(現在国立文楽劇場がある辺り)に人形芝居の小屋を持つ。これが明治の文楽座へと繋がるのである。
明治になると、政府は新たに作られた松島の地に、遊廓や芝居などの歓楽地を集中しようとし、文楽の芝居もその方針に従って松島の地に移った。松島文楽座である。しかし、当時の松島は不便な地であり、集客に不便であったので、政府の規制がゆるんだ明治17年には御堂筋御霊神社の境内に移転した。これが明治の文楽全盛期として知られる御霊分楽座である。この時代、太夫に2代竹本越路太夫(後の摂津大掾)、三味線に2代豊沢団平、人形に初代吉田玉造という名人を擁して、人形芝居始まって以来の三人紋下(芝居の座頭に相当する。普通は太夫のみが紋下となる。)となり、文楽は大いに繁栄する。が、やがて三味線の団平は文楽座を去ってライバルの彦六座に移り、越路太夫の後輩の3代大隅太夫を育てて対抗する。彦六座は、稲荷座、近松座と、経営者や座名を変えつつ文楽座に対抗するが、大正期に入るとついに滅亡する。ここに、人形芝居の本格的な座は文楽座のみとなり、この頃から「文楽」即ち人形浄瑠璃という呼称が一般化してくる。
文楽座の方も、それでは順風満帆であったかというと、そうではなく、名人摂津大掾、2代津太夫、三味線の5代広助、人形の初代玉造、紋十郎などを擁しながら、経営は苦しく、明治42年(1909)ついに植村家は文楽を新鋭の興業会社松竹合名会社に売り渡す。これから、松竹が経営難からやむなく文楽を手放して国や地元の補助によって作られた文楽協会に移行する昭和38年まで、松竹経営の文楽の時代が始まるのである。
|
|
|
|
|