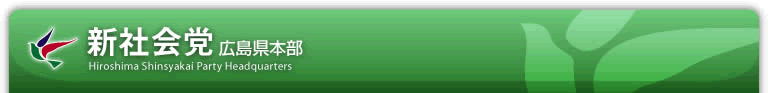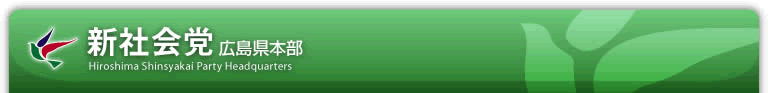|
|
|
【6月号】第36回 抗日統一戦線・第二次国共合作へ
|
|
2007/06/11
|
社会主義の歩みと将来への展望
個人の尊厳と死せ立的連帯を求めて
広島大学名誉教授 北西 允
第36回 抗日統一戦線・第二次国共合作へ
第一次国共合作は、蒋介石(1887〜1975)の反共「上海クーデター」(1927 )によって崩壊した。クーデター後、蒋介石は、武漢からさらに「北伐」を進めながら各地で共産党を攻撃し続けた。共産党は南○蜂起、各地でのソビエト政権樹立、「広東コミューン」など一連の企てに失敗し、この間リーダーも陳独秀から翟秋白(1899〜1935 )、さらに李立三(1899〜1967)へ交替した。
李立三は、中国を大恐慌下における世界資本主義体制の矛盾の焦点とみなし、中国こそ世界革命の起爆庫だとの観点から、都市蜂起を通じてソビエト政権を樹立する方針をとった。だが、李立三が指導する諸都市の蜂起はことごとく失敗に終わり、共産党は多数の犠牲者を出すとともに、根拠地喪失の危機にもさらされた。李立三はコミンテルンに召還され、替わって共産党指導部を襲ったのは、モスクワから送り込まれた王明(1904〜1974)らの留学生グループであった。彼らは、李立三一派をトロツキーストとして粛清したため、党内は一時大混乱に陥ったが、その中からやがで毛沢東が頭角を現してくる。
一方蒋介石は、自己の支配下に国の統一をはかるべく「北伐」を続け、1928年には遂に北京を手中に収めた。ところが東北地方(満州)南半分に権益を持つ日本(関東軍)が、張作霖爆殺事件、柳条湖事件を仕組んで東北地方全土を制圧し、さらに華北を窺う姿勢をみせた。日本は、1932年、華中でも「上海事変」を引き起こして新たな中国侵略に乗り出してきた。列強の注目がこの事件に注がれている間に、日本は同年、傀儡国(満州国)を東北地方に誕生させた。
蒋介石は日本軍の侵略に直面して、共産党討伐の勢いを削がれた。共産党は、1931年生き残った根拠地の代表を瑞金に集め、中華ソビエト共和国の樹立を宣言し、毛沢東を臨時主席に選出するとともに対日宣戦を布告した。だが瑞金は1934年国民党軍の手に落ち、共産党はやむなく「長征」によって僻地、延安に根拠地を移さざるを得なくなった。毛沢東は、そこから抗日民族統一戦線の構築を呼びかけた。 張作霖の息子・張学良(1901〜2001)は、父の残死後、蒋介石に恭順の意を表すようになったが、共産党の唱える抗日統一戦線の構築に耳を傾けるようになり、共産党軍党閥を督戦するため西安を訪れた蒋介石を幽閉し、しぶる彼を説得して抗日戦争遂行のため共産党との和睦を認めさせた(西安事件)。これによつて翌1937年、第2次国共合作が成立したのである。
|
|
|
|
|